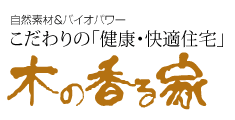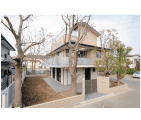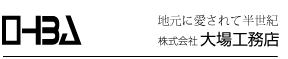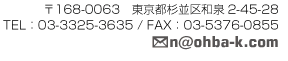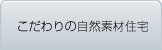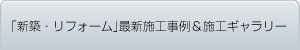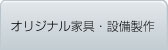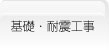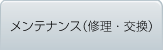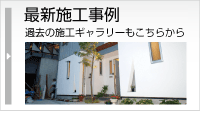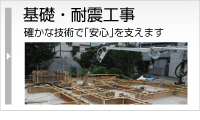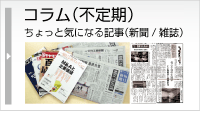構造設計からの一貫施工もお任せ下さい
 土台は、建物全体をまとめて、基礎の上にのせ、建物の高さ関係の基準となると同時に、基礎との接触による摩擦抵抗とアンカーボルトによって建物の移動を防止したり、引く抜きに耐えたりする役割があり、昔から土台をしっかりしたものにするということが大切にされてきました。したがって、建物の高さの基準になりますから、土台の高さ、水平は最初にキチンと設定しておかなければ、後の工程において問題を表面化させることになります。
土台は、建物全体をまとめて、基礎の上にのせ、建物の高さ関係の基準となると同時に、基礎との接触による摩擦抵抗とアンカーボルトによって建物の移動を防止したり、引く抜きに耐えたりする役割があり、昔から土台をしっかりしたものにするということが大切にされてきました。したがって、建物の高さの基準になりますから、土台の高さ、水平は最初にキチンと設定しておかなければ、後の工程において問題を表面化させることになります。
一方、土台は使用される木材の中で最も地面に近く、陽もあたらず、地面から湿気の影響を受けやすいため腐朽菌が繁殖しやすい場所でもあります。ということは、年数が経過してくると腐れやすい箇所ということがいえます。
地震大国である日本において、耐震構造は不可欠な要素です。建築費を抑えるために筋交いの数を減らしたり、鉄筋の本数を減らしたりといったことは問題外ですが、基礎の土台部分においては腐朽菌を繁殖させないなど、最新の注意を払う必要があります。
大場工務店は、文字通り土台からしっかり支える工法で、皆様の大切な財産である住宅を基礎からサポートします。
■地盤補強鋼管杭工法
| 鋼管杭工法とは、建物の荷重を小径構造用鋼管杭を介して強固な地盤に伝えることにより、支持力の確保及び、沈下の抑制を 図る工事です。柱状改良工事や表層改良工事と違い、地盤自体を改良し固めるのではなく、深い位置にある固い地盤(支持層)に杭を打設し、その杭で基礎を支える工事です。 【特徴】 改良材等を使用しないことにより残土が発生しません。 JIS鋼管杭使用で品質が一定しています。 施工後の養生期間が必要なく、回転圧入のため振動がありません。建築規模・敷地状況に合わせて、経済的な設計が出来、 将来の建賛時の杭の引き抜きが容易です。 |
 |
 |
| 材料(鋼管)を搬入します。 | 杭芯に鋼管をセットし打設します。 |
■柱状改良工法
| 家の基礎部に沿って地面を筒状に掘削し、そこにセメント系固化材を流し込み地中に柱状の支持体を作ります。 騒音と振動が低く残土の少ない工法で、中層改良に適しています。 地盤条件の制約を受けないため、ほとんどの地盤で工事ができます。 【乾式柱状改良工法】 アースオーガー等の機材で掘削した孔に、掘削した土砂とセメント系固化材を混合した土を埋め戻し、オーガーの正転、逆転によって攪拌、締め固めを行い、柱状の改良体を形成する工法です。湿式等に比べて費用が安くつき、養生期間が不要で硬化に伴う収縮が少ない反面、地下水位がある場合や設計深さまで崩れることなく掘削できない場合はこの工法はとれません。 【湿式柱状改良工法】 粉体のセメント系固化材と水を、あらかじめプラントで攪拌してセメントミルクを作り、それをポンプで圧送し、ロッドの先から吐出させて、地中で土とスラリー状になるまで混合攪拌して杭を作ります。支持層がない場合や地下水位がある場合でも水が流動していない限り施工が可能なので、ほとんどの地盤に対応ができます。しかし他の工法に比べて少々割高になります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
■根切・割栗・転圧工事から耐震補強、鋼製束までの基礎づくり
 |
 |
 |
| 根切・割栗・転圧工事 | 防湿フイルム工事 | 仮ベースコンクリート工事 |
 |
 |
 |
| 配筋工事 | コンクリート打設完了 | 基礎立上コンクリート打設完了 |
 |
 |
 |
| 基礎完了 | 構造材搬入:宮城県くりこま燻煙加工材 | 登り梁は8寸(24cm) |
 |
 |
 |
| 吹き抜け部分は9寸通柱 (27cm) | ||
 |
 |
 |
| 耐震補強 ホールダウン金物の取り付け | 鋼製束 | |